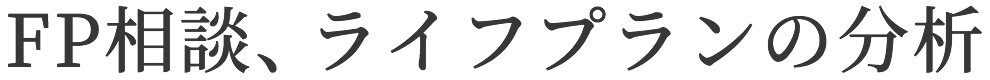家を探し始める
物件探しは“日々の散歩”から
仕事の配属先が決まり、ようやく生活も落ち着いてきた30代前半の頃。ファイナンシャルプランナーとして住宅展示場やお客様のご自宅などで日々住宅相談に乗っていました。
住宅展示場に来るお客様の多くがベビーカーを押しており、第2子を妊娠しているという方の話を聞くと、
「一人目の出産のときも探していたけれど、つわりが大変だったり、子どもが産まれてからの生活が想像できなくて諦めてしまった。2人目が産まれるとまた大変だから、このタイミングで検討したい」
という声が多く聞かれました。
「自分たちも、そろそろかな?」
そんな気持ちで、漠然と住宅購入を意識し始めました。とはいえ、強い動機があったわけではなく、
「今のうちに買っておかないと、ローンが65歳までに終わらなくなるな…」
というライフプラン的な要因もありました。
当時私たちが住んでいたのは、京王線沿い、駅から徒歩2分の古めの2DKマンション。地域性も治安も良く、近所には公園もスーパーも揃っていて、とても便利な場所でした。
ただ、建物自体は老朽化が進み、1階のオートロックの自動ドアが故障して開けっ放しになったり、気温の上昇で窓のサッシが歪んでしまったりと、快適とは言い難い状況もありました。
また、子育て世代の多いマンションだったこともあり、夜泣きや足音など生活音が少しずつ気になるようになっていました。
そんな中、よく行く散歩道で「ここにマンションが建ちます」と書かれた看板や、販売予定のチラシを目にする機会が増え、自然と足は住宅展示場に向いていました。
「ねえ、マンションの展示場ができたみたいだから行ってみる?」
そんな軽い気持ちで住宅探しが始まりました。
住宅展示場に来るお客様の多くがベビーカーを押しており、第2子を妊娠しているという方の話を聞くと、
「一人目の出産のときも探していたけれど、つわりが大変だったり、子どもが産まれてからの生活が想像できなくて諦めてしまった。2人目が産まれるとまた大変だから、このタイミングで検討したい」
という声が多く聞かれました。
「自分たちも、そろそろかな?」
そんな気持ちで、漠然と住宅購入を意識し始めました。とはいえ、強い動機があったわけではなく、
「今のうちに買っておかないと、ローンが65歳までに終わらなくなるな…」
というライフプラン的な要因もありました。
当時私たちが住んでいたのは、京王線沿い、駅から徒歩2分の古めの2DKマンション。地域性も治安も良く、近所には公園もスーパーも揃っていて、とても便利な場所でした。
ただ、建物自体は老朽化が進み、1階のオートロックの自動ドアが故障して開けっ放しになったり、気温の上昇で窓のサッシが歪んでしまったりと、快適とは言い難い状況もありました。
また、子育て世代の多いマンションだったこともあり、夜泣きや足音など生活音が少しずつ気になるようになっていました。
そんな中、よく行く散歩道で「ここにマンションが建ちます」と書かれた看板や、販売予定のチラシを目にする機会が増え、自然と足は住宅展示場に向いていました。
「ねえ、マンションの展示場ができたみたいだから行ってみる?」
そんな軽い気持ちで住宅探しが始まりました。
マンションのモデルルーム
最初に見に行ったのはマンションのモデルルーム。
インテリアや照明の演出で高級感はありましたが、実際の間取りを冷静に見ると、収納スペースが少なく、生活動線が狭い。子どもが増えたときの生活を想像すると、少し無理があるなと感じました。
価格帯が安い理由を若い女性の営業の方に質問したところ、明確な理由も示されず、
「この物件はお買い得ですよ」
とばかりに勧めてくる様子に、妻は納得がいかないようでした。
ただ、近隣の新築マンションの相場よりも安く、駅から徒歩3分で4,000万円台中盤という価格帯は魅力的でした。私たち家族とはご縁がなかったものの、やはり数日で全て完売したようで、なかなかのお買い得物件だったようです。
インテリアや照明の演出で高級感はありましたが、実際の間取りを冷静に見ると、収納スペースが少なく、生活動線が狭い。子どもが増えたときの生活を想像すると、少し無理があるなと感じました。
価格帯が安い理由を若い女性の営業の方に質問したところ、明確な理由も示されず、
「この物件はお買い得ですよ」
とばかりに勧めてくる様子に、妻は納得がいかないようでした。
ただ、近隣の新築マンションの相場よりも安く、駅から徒歩3分で4,000万円台中盤という価格帯は魅力的でした。私たち家族とはご縁がなかったものの、やはり数日で全て完売したようで、なかなかのお買い得物件だったようです。
住宅を購入する上での条件
我が家にとって最も重要だったのは、“妻の実家との距離感”でした。
妻は大家族で育ち、実家には祖父母、曾祖母、両親、兄弟4人を含め、最大で9人が暮らしていたこともあります。埼玉県の田舎育ちの私にとって、都内のサザエさんのようなにぎやかな家庭で初めて食卓を囲んだときの衝撃は今でも忘れられません。
義両親にとっても、私たちの娘が初孫だったこともあり、とても可愛がってくれていたため、なるべく近くに住みたいという想いが私にも自然と芽生えていました。
価格帯としては、我が家の収入から見て安くて5,000万円〜高くても6,500万円を想定。ローンはペアで組むかは物件次第で、できれば私一人で組みたかったのですが、生命保険の募集人という個人事業主の立場では、単独での融資はやや難しい状況でした。その点も、妻と義両親は理解してくれていました。
「住宅購入は恋愛と同じ。運命の出会いがあったら、そのタイミングで真剣に考えた方がいい」
そうお客様に話していた私自身が、まさにそのタイミングを迎えようとしていたのです。
妻は大家族で育ち、実家には祖父母、曾祖母、両親、兄弟4人を含め、最大で9人が暮らしていたこともあります。埼玉県の田舎育ちの私にとって、都内のサザエさんのようなにぎやかな家庭で初めて食卓を囲んだときの衝撃は今でも忘れられません。
義両親にとっても、私たちの娘が初孫だったこともあり、とても可愛がってくれていたため、なるべく近くに住みたいという想いが私にも自然と芽生えていました。
価格帯としては、我が家の収入から見て安くて5,000万円〜高くても6,500万円を想定。ローンはペアで組むかは物件次第で、できれば私一人で組みたかったのですが、生命保険の募集人という個人事業主の立場では、単独での融資はやや難しい状況でした。その点も、妻と義両親は理解してくれていました。
「住宅購入は恋愛と同じ。運命の出会いがあったら、そのタイミングで真剣に考えた方がいい」
そうお客様に話していた私自身が、まさにそのタイミングを迎えようとしていたのです。
野村不動産プラウドとの出会い、そして現実
野村不動産プラウド
ある日、近所を散歩していると、建築予定のマンションの看板を見つけました。そこに建つのは、あの有名な野村不動産の「プラウド」3LDKマンション。
南向きで前面道路は一方通行、裏手には大きな公園が広がるという、まさに子育てに理想的な立地。駅から徒歩10分、スーパーは少し遠いものの、生活圏としては申し分ありませんでした。
私のお客様でも実際に購入された方や、賃貸で住んでいる方がいて、よく知っているブランドでした。好立地に建つことが多く、資産性という観点でも値下がりしづらい。将来売却することを考えても、ネームバリューのある物件でした。
「これは……」と感じ、できたばかりのモデルルームへ足を運び、資金シミュレーションも提示してもらいました。検討していたのは、南向き2階の中部屋で、価格は約6,300万円。初期販売時期ということもあり、条件としては悪くありませんでした。
住環境もよく知っている地域ということもあり、
「これ、買いじゃない?」
と内心思いながらも、妻の様子を見て、一晩持ち帰って考えることにしました。
その夜、妻と真剣に話し合いました。
「もし本気で欲しいなら、これからもう一度行って申し込みしてくるよ。売れちゃったら残念でしょ」
そう伝えると、妻は少し沈黙したあと、
「……ちょっと気になるところがあるの。管理費と修繕費、どうなってるか確認してくれない?」
かなり真剣に考えている様子でした。
その場で担当者に電話をして確認したところ、驚きの事実が。
「管理費と修繕費は5年ごとに5,000円ずつ上がっていきます。最大で月4万〜5万円を予定しています」
「さすがプラウド、強気だな……」
私は「ギリギリいけるかも」と思いましたが、妻は
「教育費がピークになる15年後〜20年後にこの負担はきついと思う」
と、はっきり断りました。
この時、勢いで購入しなかった妻の冷静な判断に、私は心から感謝しました。
感覚で動きがちな私と、慎重に判断する妻──まさにバランスの取れた関係だと実感しました。
それでも、「あの家に住んでいたらどうだっただろう」と、今でも時々想像してしまうほど、立地も含め魅力的なマンションでした。
南向きで前面道路は一方通行、裏手には大きな公園が広がるという、まさに子育てに理想的な立地。駅から徒歩10分、スーパーは少し遠いものの、生活圏としては申し分ありませんでした。
私のお客様でも実際に購入された方や、賃貸で住んでいる方がいて、よく知っているブランドでした。好立地に建つことが多く、資産性という観点でも値下がりしづらい。将来売却することを考えても、ネームバリューのある物件でした。
「これは……」と感じ、できたばかりのモデルルームへ足を運び、資金シミュレーションも提示してもらいました。検討していたのは、南向き2階の中部屋で、価格は約6,300万円。初期販売時期ということもあり、条件としては悪くありませんでした。
住環境もよく知っている地域ということもあり、
「これ、買いじゃない?」
と内心思いながらも、妻の様子を見て、一晩持ち帰って考えることにしました。
その夜、妻と真剣に話し合いました。
「もし本気で欲しいなら、これからもう一度行って申し込みしてくるよ。売れちゃったら残念でしょ」
そう伝えると、妻は少し沈黙したあと、
「……ちょっと気になるところがあるの。管理費と修繕費、どうなってるか確認してくれない?」
かなり真剣に考えている様子でした。
その場で担当者に電話をして確認したところ、驚きの事実が。
「管理費と修繕費は5年ごとに5,000円ずつ上がっていきます。最大で月4万〜5万円を予定しています」
「さすがプラウド、強気だな……」
私は「ギリギリいけるかも」と思いましたが、妻は
「教育費がピークになる15年後〜20年後にこの負担はきついと思う」
と、はっきり断りました。
この時、勢いで購入しなかった妻の冷静な判断に、私は心から感謝しました。
感覚で動きがちな私と、慎重に判断する妻──まさにバランスの取れた関係だと実感しました。
それでも、「あの家に住んでいたらどうだっただろう」と、今でも時々想像してしまうほど、立地も含め魅力的なマンションでした。
祖母の土地の贈与
転機となった“祖母の土地”
プラウドの件をきっかけに、住宅への関心がさらに高まりました。
そんな中で浮上したのが、妻の祖母が所有する土地の存在でした。
場所は埼玉県さいたま市、某駅から徒歩7分という好立地。もともと親戚から相続した土地で、長らく青空駐車場として貸していたとのこと。当時の会社からも近く、現地を確認したところ、「ここに家が建てられたら最高だな」と強く感じました。
埼玉の片田舎出身の私にとって、この土地の資産性の高さは一目見ただけでわかるものでした。
しかし、義理の父はかなり頑固な性格で、特に理由もなく「簡単に土地を渡すわけにはいかない」とのスタンスを取っていました。
そこで、妻が動きました
そんな中で浮上したのが、妻の祖母が所有する土地の存在でした。
場所は埼玉県さいたま市、某駅から徒歩7分という好立地。もともと親戚から相続した土地で、長らく青空駐車場として貸していたとのこと。当時の会社からも近く、現地を確認したところ、「ここに家が建てられたら最高だな」と強く感じました。
埼玉の片田舎出身の私にとって、この土地の資産性の高さは一目見ただけでわかるものでした。
しかし、義理の父はかなり頑固な性格で、特に理由もなく「簡単に土地を渡すわけにはいかない」とのスタンスを取っていました。
そこで、妻が動きました
進まない相続を強行突破
「もう話が進まないなら、勝手にプラン作っちゃおう」
そう言って、妻は私に法務局へ行かせて土地の謄本を取り寄せさせ、「この土地に家を建てるからね!」と実家に宣言してきてしまいました。
その熱意に、少しずつ周囲も動き始めたのです。
そう言って、妻は私に法務局へ行かせて土地の謄本を取り寄せさせ、「この土地に家を建てるからね!」と実家に宣言してきてしまいました。
その熱意に、少しずつ周囲も動き始めたのです。
ハウスメーカーの住宅展示巡り
週末は、モデルハウスの展示場巡りが私たち夫婦の楽しみになっていました。各地の住宅展示場に足を運び、数多くの物件を見て回りました。
展示場では記名や名刺の提出が必要な場面も多くありましたが、私も自分の名刺を渡していたこともあり、営業の方たちも「無理に営業しても意味がない」と判断してくれたのか、その後の電話営業などはほとんどありませんでした。
最初にプランを作ってもらったのはヘーベルハウス。頑丈な構造と洗練された外観に魅力を感じましたが、当時の坪単価が90万円超と高額。とはいえ、「この建物は絶対に崩れない」という安心感は抜群で、営業の方も「4,000万円以上はかかりますが、そのぶん最高の家にします」とはっきり言ってくれるような信頼感のある方でした。
しかし、妻の好みに合わなかったこともあり、「今回はご縁がなかったということで」と丁寧にお断りすることになりました。
展示場では記名や名刺の提出が必要な場面も多くありましたが、私も自分の名刺を渡していたこともあり、営業の方たちも「無理に営業しても意味がない」と判断してくれたのか、その後の電話営業などはほとんどありませんでした。
最初にプランを作ってもらったのはヘーベルハウス。頑丈な構造と洗練された外観に魅力を感じましたが、当時の坪単価が90万円超と高額。とはいえ、「この建物は絶対に崩れない」という安心感は抜群で、営業の方も「4,000万円以上はかかりますが、そのぶん最高の家にします」とはっきり言ってくれるような信頼感のある方でした。
しかし、妻の好みに合わなかったこともあり、「今回はご縁がなかったということで」と丁寧にお断りすることになりました。
住友林業で決まり?
積水ハウスの検討と同時に、同じ住宅展示場内にあった住友林業のモデルハウスにも足を運んでみました。
展示場に一歩足を踏み入れた瞬間、ふわっと漂う“木の香り”がとても心地よく、第一印象から強く惹かれたのを覚えています。自然素材に包まれた空間には、なんとも言えない安心感があり、「これは他とちょっと違うな」と直感的に感じました。
対応してくれたのは、展示場の店長を務める方。経験も知識も豊富で、こちらの話にもじっくり耳を傾けてくれる信頼できる方でした。
ちょうどタイミングよく、住友林業で建築された完成物件が3件ほど公開されており、実際に内覧することができました。また、数年前に住友林業で建てたという実際のお客様のご厚意で、そのご自宅に訪問させていただく機会にも恵まれました。住みながらのリアルな空間を見せていただけたのは、非常に貴重な体験でした。
外壁のデザインにも選択肢が豊富で、サイディング・吹き付け・タイル貼りなど、見た目の質感を自分たちの好みに合わせられるのも魅力のひとつ。特に、吹き付け外壁にアクセントでタイルをあしらったスタイルは高級感があり、「これはいいな」と感じたのをよく覚えています。
設備や仕様にもこだわりたい私たちにとって、キッチンや浴室などのオプションをしっかりつけても、建物本体の価格が3,500万円前後に収まるというのは想定内の範囲。決して安くはないですが、それだけの価値を感じられる内容でした。
さらに、住友林業の特徴として印象的だったのが、設計士との個別打ち合わせ制度です。正式な図面を描いてもらうには5万円ほどの費用がかかりますが、それでもお願いする価値があると判断しました。
他のハウスメーカーでは営業担当との打ち合わせが中心なのに対し、ここでは一級建築士と直接対話ができる──これは非常に大きなポイントでした。
実際に設計士さんとの打ち合わせを重ねる中で、太陽の動きや風通し、空間の抜け感、トイレや収納の位置など、素人では気づけない視点からさまざまな提案をしていただきました。
自分たちの頭の中になかったような斬新なプランを目にするたびに、図面を通じて家づくりの可能性がどんどん広がっていくのが楽しくて、夢中になっていきました。
この頃には、すでに複数のハウスメーカーで図面を引いてもらっていたこともあり、私たち自身の知識や判断力もだいぶ高まっていたと感じています。
そして、納得のいく図面が完成したタイミングで、妻がその図面を義父に提出しました。
「もうこのプランで進めるから」
私はその場にはいませんでしたが、義父は「そうですか」とだけ答え、図面には目も通さなかったそうです。
実の娘(妻)が真剣に考えて来たんだからもっとワクワクしながらみてくれよと内心思いました。
ところが数日後、話が急展開を迎えることになります──。
展示場に一歩足を踏み入れた瞬間、ふわっと漂う“木の香り”がとても心地よく、第一印象から強く惹かれたのを覚えています。自然素材に包まれた空間には、なんとも言えない安心感があり、「これは他とちょっと違うな」と直感的に感じました。
対応してくれたのは、展示場の店長を務める方。経験も知識も豊富で、こちらの話にもじっくり耳を傾けてくれる信頼できる方でした。
ちょうどタイミングよく、住友林業で建築された完成物件が3件ほど公開されており、実際に内覧することができました。また、数年前に住友林業で建てたという実際のお客様のご厚意で、そのご自宅に訪問させていただく機会にも恵まれました。住みながらのリアルな空間を見せていただけたのは、非常に貴重な体験でした。
外壁のデザインにも選択肢が豊富で、サイディング・吹き付け・タイル貼りなど、見た目の質感を自分たちの好みに合わせられるのも魅力のひとつ。特に、吹き付け外壁にアクセントでタイルをあしらったスタイルは高級感があり、「これはいいな」と感じたのをよく覚えています。
設備や仕様にもこだわりたい私たちにとって、キッチンや浴室などのオプションをしっかりつけても、建物本体の価格が3,500万円前後に収まるというのは想定内の範囲。決して安くはないですが、それだけの価値を感じられる内容でした。
さらに、住友林業の特徴として印象的だったのが、設計士との個別打ち合わせ制度です。正式な図面を描いてもらうには5万円ほどの費用がかかりますが、それでもお願いする価値があると判断しました。
他のハウスメーカーでは営業担当との打ち合わせが中心なのに対し、ここでは一級建築士と直接対話ができる──これは非常に大きなポイントでした。
実際に設計士さんとの打ち合わせを重ねる中で、太陽の動きや風通し、空間の抜け感、トイレや収納の位置など、素人では気づけない視点からさまざまな提案をしていただきました。
自分たちの頭の中になかったような斬新なプランを目にするたびに、図面を通じて家づくりの可能性がどんどん広がっていくのが楽しくて、夢中になっていきました。
この頃には、すでに複数のハウスメーカーで図面を引いてもらっていたこともあり、私たち自身の知識や判断力もだいぶ高まっていたと感じています。
そして、納得のいく図面が完成したタイミングで、妻がその図面を義父に提出しました。
「もうこのプランで進めるから」
私はその場にはいませんでしたが、義父は「そうですか」とだけ答え、図面には目も通さなかったそうです。
実の娘(妻)が真剣に考えて来たんだからもっとワクワクしながらみてくれよと内心思いました。
ところが数日後、話が急展開を迎えることになります──。
土地贈与にまつわる急展開
義父が知り合いの税理士に相談し、今さらながら土地の評価と贈与にかかる税額の試算を行ったとのこと。祖母の所有地とはいえ、価値のある土地を一人の孫(妻)に贈与するというのは不平等になるとの懸念から、親族全員の承諾が必要だという話になりました。
義父の姉(伯母)に了解を取りつけ、さらに孫たち7人全員に「贈与に異議はない」という内容の承諾書にサインをもらう流れに。
「まあ、それでもしっかり話が進むならありがたいことだ」と思っていたのですが、そこからさらに一波乱ありました。
祖母の所有する土地には明確な資産価値があるため、「贈与として受け取るのであれば、土地代は支払うべきだ」と義父から申し出がありました。
最終的に、契約書が作成され「月々〇〇万円、〇年間にわたって分割で土地代を支払う」という条件で正式に土地を贈与してもらうこととなりました。
義父の姉(伯母)に了解を取りつけ、さらに孫たち7人全員に「贈与に異議はない」という内容の承諾書にサインをもらう流れに。
「まあ、それでもしっかり話が進むならありがたいことだ」と思っていたのですが、そこからさらに一波乱ありました。
祖母の所有する土地には明確な資産価値があるため、「贈与として受け取るのであれば、土地代は支払うべきだ」と義父から申し出がありました。
最終的に、契約書が作成され「月々〇〇万円、〇年間にわたって分割で土地代を支払う」という条件で正式に土地を贈与してもらうこととなりました。
そして振り出しに戻る
数多くのハウスメーカーと打ち合わせを重ね、自分たちなりに知識を深めて練り上げた理想のプラン。
しかし、そこに土地代が追加されたことで、建物価格3,500万〜4,000万円に土地費用が加わり、想定予算を大幅にオーバーする事態に。
「一体、今までの時間は何だったんだ……。それならもっと早く言ってくれよ」
思わずそう漏らしてしまいたくなるような気持ちでした。
「まあ、土地がもらえるんだから仕方ないよね。もう少しグレードを下げて、価格帯の安い工務店にするしかないね」
そんなふうに話しながら、妻の現実的な表情がなんとも言えない切なさを物語っていました。
世の中の相続や贈与というのは、なかなかスムーズにいかない──その現実を身をもって体感した瞬間でした。
それでも、自分たちでは到底手の届かないほどの好立地な土地を譲り受けられることには変わりありません。いろいろありますが有り難い限りです。
しかし、そこに土地代が追加されたことで、建物価格3,500万〜4,000万円に土地費用が加わり、想定予算を大幅にオーバーする事態に。
「一体、今までの時間は何だったんだ……。それならもっと早く言ってくれよ」
思わずそう漏らしてしまいたくなるような気持ちでした。
「まあ、土地がもらえるんだから仕方ないよね。もう少しグレードを下げて、価格帯の安い工務店にするしかないね」
そんなふうに話しながら、妻の現実的な表情がなんとも言えない切なさを物語っていました。
世の中の相続や贈与というのは、なかなかスムーズにいかない──その現実を身をもって体感した瞬間でした。
それでも、自分たちでは到底手の届かないほどの好立地な土地を譲り受けられることには変わりありません。いろいろありますが有り難い限りです。
新たなハウスメーカー県民共済住宅
埼玉県民共済住宅との出会い
プランが振り出しに戻り、改めて新たな選択肢を探す中で、一連の流れを会社の先輩に相談したところ、
「それなら、埼玉県民共済住宅に行ってみたら? 安くて評判もいいよ」
というアドバイスをもらいました。
正直、それまで“共済”と聞いてイメージするのは、スーツや保険といった分野ばかりで、「家を建てる」という選択肢としては頭にありませんでした。
しかし実際に足を運んでみると、その印象は大きく覆されました。
大手ハウスメーカーと同じ無垢材を使用し、外壁にはヘーベルハウスと同様の素材を選ぶことも可能。見た目にも十分な高級感があり、何より価格が魅力的でした。
幸い、住友林業でほぼ完成していた間取り図があったため、話もスムーズに進みました。
週末に次の打ち合わせの予約を入れ、県民共済住宅とのやり取りがスタート。
担当してくださったのは、一級建築士の設計士さん。営業マンは存在せず、最初からプロの設計士と直接打ち合わせができるというスタイルに、非常に合理性を感じました。
設計士さんは大手メーカーから転職してきたベテランで、図面作成のスピードも正確性も申し分なし。
「ここではたくさん図面を描けるから楽しいですよ」
と笑いながら話す姿に、誠実さとプロ意識を感じました。
これまで悩んでいた「トイレの位置」や「階段下のスペース活用」などの細かい点にも、設計士ならではの視点からスパッと明快に提案をしてもらえたことがとても印象的でした。
ただ、県民共済住宅のスタンスとしては「お客様の要望をそのまま正確に図面化する」というものなので、ある程度明確なビジョンがないと良いプランは生まれにくいとも感じました。
とはいえ、それまで多くのメーカーと打ち合わせをしてきた経験がここで一気に活かされ、間取り・外壁・オプションなど、あらかじめ決めていた内容をスムーズに落とし込むことができました。
「これで決まりだね」
そう話してから数日後、私たちは正式に契約することとなりました。
「それなら、埼玉県民共済住宅に行ってみたら? 安くて評判もいいよ」
というアドバイスをもらいました。
正直、それまで“共済”と聞いてイメージするのは、スーツや保険といった分野ばかりで、「家を建てる」という選択肢としては頭にありませんでした。
しかし実際に足を運んでみると、その印象は大きく覆されました。
大手ハウスメーカーと同じ無垢材を使用し、外壁にはヘーベルハウスと同様の素材を選ぶことも可能。見た目にも十分な高級感があり、何より価格が魅力的でした。
幸い、住友林業でほぼ完成していた間取り図があったため、話もスムーズに進みました。
週末に次の打ち合わせの予約を入れ、県民共済住宅とのやり取りがスタート。
担当してくださったのは、一級建築士の設計士さん。営業マンは存在せず、最初からプロの設計士と直接打ち合わせができるというスタイルに、非常に合理性を感じました。
設計士さんは大手メーカーから転職してきたベテランで、図面作成のスピードも正確性も申し分なし。
「ここではたくさん図面を描けるから楽しいですよ」
と笑いながら話す姿に、誠実さとプロ意識を感じました。
これまで悩んでいた「トイレの位置」や「階段下のスペース活用」などの細かい点にも、設計士ならではの視点からスパッと明快に提案をしてもらえたことがとても印象的でした。
ただ、県民共済住宅のスタンスとしては「お客様の要望をそのまま正確に図面化する」というものなので、ある程度明確なビジョンがないと良いプランは生まれにくいとも感じました。
とはいえ、それまで多くのメーカーと打ち合わせをしてきた経験がここで一気に活かされ、間取り・外壁・オプションなど、あらかじめ決めていた内容をスムーズに落とし込むことができました。
「これで決まりだね」
そう話してから数日後、私たちは正式に契約することとなりました。
ついに始まった家作り
契約してから着工までは数ヶ月の待機期間があり、その間に「土地の整地」を別の業者に依頼することにしました。
あわせて「外構工事」についても検討を進めました。土地は更地だったため、当初の見積もりは90万円程度。しかし実際に掘ってみると、お隣の塀が基礎まで入っておらず、「これ以上掘ると崩れてしまう可能性がある」と現場担当者から工事の一時中断を告げられました。
外構業者からは「地中にH鋼(エイチこう)を入れて補強しましょう」と提案があり、やむなく150万円ほどの追加予算を組むことに。
こうした“想定外の出費”も、家づくりあるあるなのだと痛感しました。
さらに、整地後には登記に必要な正確な測量も実施。祖母の代から管理されていた土地とはいえ、境界が曖昧になっていた箇所もあり、改めて測量し直して登記を済ませました。
当時、妻は次女を妊娠中であったため、現場確認や近隣への挨拶回りなどは私が主に担当。現場は徐々に骨組みが立ち上がり、建物としての形が見え始めていきました。
あわせて「外構工事」についても検討を進めました。土地は更地だったため、当初の見積もりは90万円程度。しかし実際に掘ってみると、お隣の塀が基礎まで入っておらず、「これ以上掘ると崩れてしまう可能性がある」と現場担当者から工事の一時中断を告げられました。
外構業者からは「地中にH鋼(エイチこう)を入れて補強しましょう」と提案があり、やむなく150万円ほどの追加予算を組むことに。
こうした“想定外の出費”も、家づくりあるあるなのだと痛感しました。
さらに、整地後には登記に必要な正確な測量も実施。祖母の代から管理されていた土地とはいえ、境界が曖昧になっていた箇所もあり、改めて測量し直して登記を済ませました。
当時、妻は次女を妊娠中であったため、現場確認や近隣への挨拶回りなどは私が主に担当。現場は徐々に骨組みが立ち上がり、建物としての形が見え始めていきました。
建築の進行と現場の様子
建築が進むにつれ、いよいよ私たちが選んだ設備や仕様がカタチになって現れてきました。
キッチンや浴室、トイレなどの設備は、TOTO・LIXIL・Panasonicなどのショールームを回って選びました。積水ハウスなど大手メーカーであればオプション扱いで数百万円かかるような設備が、県民共済住宅では標準仕様に含まれていることが多く、価格の面でも納得感がありました。
その後、電気の配線やコンセントの位置などを現場で確認。照明の配置やスイッチの高さ、数、位置など、細かな部分を詰めていく作業が続きました。
現場監督は、かつてポラスに在籍していたという丁寧な職人気質の方で、毎回細かく説明してくれるだけでなく、「ここはこうした方がいいかもしれませんね」と親身になって提案してくれたのが印象的でした。
電気の位置、収納の取り方、階段下の使い方──細部に至るまでこだわりを持ち、楽しそうに私たちの家を作ってくれている様子に、安心感と信頼感を覚えました。
打ち合わせも最終段階に入ったころ、私はふと気づきました。
「……家の中のこと、俺が決めたもの、ひとつもないな」
それもそのはず。これまでの打ち合わせで家の内部に関してはほぼすべて彼女の意見が反映されていました。土地を贈与してもらう立場からあまり意見を言わず黒子に徹していたのです。
それでも「最後の悪あがき」として、ベランダの手すりのグレードを少しだけ上げさせてもらい、裏庭の小さなスペースにウッドデッキを設置することをお願いしました。
結局、私の意見が取り入れられたのは“外側”だけ。
それでも妻の希望だったキッチンや収納棚の追加オプションもつけて、建物価格は約1,900万円に収めることができました。
キッチンや浴室、トイレなどの設備は、TOTO・LIXIL・Panasonicなどのショールームを回って選びました。積水ハウスなど大手メーカーであればオプション扱いで数百万円かかるような設備が、県民共済住宅では標準仕様に含まれていることが多く、価格の面でも納得感がありました。
その後、電気の配線やコンセントの位置などを現場で確認。照明の配置やスイッチの高さ、数、位置など、細かな部分を詰めていく作業が続きました。
現場監督は、かつてポラスに在籍していたという丁寧な職人気質の方で、毎回細かく説明してくれるだけでなく、「ここはこうした方がいいかもしれませんね」と親身になって提案してくれたのが印象的でした。
電気の位置、収納の取り方、階段下の使い方──細部に至るまでこだわりを持ち、楽しそうに私たちの家を作ってくれている様子に、安心感と信頼感を覚えました。
打ち合わせも最終段階に入ったころ、私はふと気づきました。
「……家の中のこと、俺が決めたもの、ひとつもないな」
それもそのはず。これまでの打ち合わせで家の内部に関してはほぼすべて彼女の意見が反映されていました。土地を贈与してもらう立場からあまり意見を言わず黒子に徹していたのです。
それでも「最後の悪あがき」として、ベランダの手すりのグレードを少しだけ上げさせてもらい、裏庭の小さなスペースにウッドデッキを設置することをお願いしました。
結局、私の意見が取り入れられたのは“外側”だけ。
それでも妻の希望だったキッチンや収納棚の追加オプションもつけて、建物価格は約1,900万円に収めることができました。
名義と住宅ローン、そして完成へ
住宅ローンについては、最終的に妻名義で組むこととなりました。
これは祖母の希望によるもので、「もし万が一離婚しても、孫娘の名義で財産を守りたい」という思いがあったようです。
支払いは私が行うのですが、形式上の名義とローン契約者は妻。新婚数年でのこの展開に、正直複雑な思いもありましたが、祖母としては「あのときはまだ大切な孫娘が嫁に取られてしまった悔しさがあった」と後から聞かされました。
結婚からすでに4年たっていなのですが、あまり信用されてなかったようです、家族とはそうゆうものなんですね。
そして、ついに建物が完成。外壁が仕上がり、シートが外されて全体が姿を現したとき、「ついにここが我が家になるんだ」と、じわじわと実感が湧いてきました。
最後の外構工事が終わり、インターフォンや表札が取り付けられた瞬間、「なかなか立派な家じゃないか」と、これまでの選択や努力に対する手応えを感じることができました。
こうして、ついに私たちの“家づくり”がひとつのカタチになったのです。
これは祖母の希望によるもので、「もし万が一離婚しても、孫娘の名義で財産を守りたい」という思いがあったようです。
支払いは私が行うのですが、形式上の名義とローン契約者は妻。新婚数年でのこの展開に、正直複雑な思いもありましたが、祖母としては「あのときはまだ大切な孫娘が嫁に取られてしまった悔しさがあった」と後から聞かされました。
結婚からすでに4年たっていなのですが、あまり信用されてなかったようです、家族とはそうゆうものなんですね。
そして、ついに建物が完成。外壁が仕上がり、シートが外されて全体が姿を現したとき、「ついにここが我が家になるんだ」と、じわじわと実感が湧いてきました。
最後の外構工事が終わり、インターフォンや表札が取り付けられた瞬間、「なかなか立派な家じゃないか」と、これまでの選択や努力に対する手応えを感じることができました。
こうして、ついに私たちの“家づくり”がひとつのカタチになったのです。
家づくりを終えて
人生設計と向き合う時間
家が建つまでの道のりは、想像以上に長く、そして複雑でした。
いくつもの住宅展示場を巡り、ハウスメーカーのプランを比較し、祖母の土地の話が出てきたかと思えば、義父との交渉、予算オーバー、土地代の支払い交渉……。
「これで決まりだ」と思った瞬間もあれば、「また最初からやり直しか」と落ち込むこともありました。
それでも、こうして無事に家が完成し、今は「全部やってよかった」と思えています。
この家づくりを通して、夫婦それぞれの育ってきた環境や、親との関係、価値観の違いに気づき、互いをより深く理解する時間にもなりました。
間取りや資金計画を超えて、「どんな暮らしをしたいのか」「これからどんな人生を送りたいのか」──そんな問いを夫婦で重ねる時間は、家そのもの以上に大きな財産になったと感じています。
いくつもの住宅展示場を巡り、ハウスメーカーのプランを比較し、祖母の土地の話が出てきたかと思えば、義父との交渉、予算オーバー、土地代の支払い交渉……。
「これで決まりだ」と思った瞬間もあれば、「また最初からやり直しか」と落ち込むこともありました。
それでも、こうして無事に家が完成し、今は「全部やってよかった」と思えています。
この家づくりを通して、夫婦それぞれの育ってきた環境や、親との関係、価値観の違いに気づき、互いをより深く理解する時間にもなりました。
間取りや資金計画を超えて、「どんな暮らしをしたいのか」「これからどんな人生を送りたいのか」──そんな問いを夫婦で重ねる時間は、家そのもの以上に大きな財産になったと感じています。
これから家を買う人、建てる人に伝えたいこと
続きにコラムについて
新生活、そして突如訪れた社会の変化
こうしてようやく新しい家が完成し、「さぁ、これからこの家での生活が始まるぞ」と期待を膨らませていた私たち。
しかしその直後──
2020年、新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言が発令され、日本全体が一変しました。
会社には出勤できず、お客様にも会えない。
妻も実家に戻ったまま、新生活どころか家族全員が揃う日すら見通しが立たない。
そんな「予想外の始まり」となった引っ越しと新生活、そして私自身の転職を決意するきっかけになった2020年の出来事について続きのコラムご是非、ご一読ください。
こうしてようやく新しい家が完成し、「さぁ、これからこの家での生活が始まるぞ」と期待を膨らませていた私たち。
しかしその直後──
2020年、新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言が発令され、日本全体が一変しました。
会社には出勤できず、お客様にも会えない。
妻も実家に戻ったまま、新生活どころか家族全員が揃う日すら見通しが立たない。
そんな「予想外の始まり」となった引っ越しと新生活、そして私自身の転職を決意するきっかけになった2020年の出来事について続きのコラムご是非、ご一読ください。