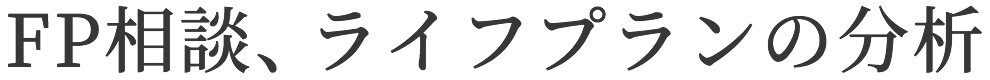妊娠・出産で気づいた、夫婦のギャップと夫の認識の甘さ
2017年2月、私たち夫婦にとって初めての子ども──長女が誕生しました。結婚して3年。私たちはあまり意識していなかったのですが、妻としては「そろそろ子どもがほしい」という気持ちが強まっていたようです。
しかし、現実はそう簡単にはいかず、妻は毎日基礎体温をつけ、排卵のタイミングをアプリでチェックするなど、妊娠に向けた努力を続けていました。
それでもなかなか授からず、「今月も妊娠しなかった……」とストレスを抱え込む日々だったそうです。
そこで不妊治療を始めることになり、クリニックで薬を処方され、定期的に通院し始めました。
一方の私はというと、ある日、妻に「今夜はタイミングだから、早く帰ってきてね」と言われていたにもかかわらず、会社の飲み会に参加し、帰宅が遅くなってしまい。
すっかり不機嫌になった妻と気まずい空気のまま過ごすことも多々ありました。
今振り返ると、本当に申し訳ないことをしたと心から思います。
正直に言えば、当時の私は女性の身体のことをなんとなく理解しているつもりでしたが、整理や妊娠のメカニズムにしての知識を深める努力はしていなかったです。
しかし、現実はそう簡単にはいかず、妻は毎日基礎体温をつけ、排卵のタイミングをアプリでチェックするなど、妊娠に向けた努力を続けていました。
それでもなかなか授からず、「今月も妊娠しなかった……」とストレスを抱え込む日々だったそうです。
そこで不妊治療を始めることになり、クリニックで薬を処方され、定期的に通院し始めました。
一方の私はというと、ある日、妻に「今夜はタイミングだから、早く帰ってきてね」と言われていたにもかかわらず、会社の飲み会に参加し、帰宅が遅くなってしまい。
すっかり不機嫌になった妻と気まずい空気のまま過ごすことも多々ありました。
今振り返ると、本当に申し訳ないことをしたと心から思います。
正直に言えば、当時の私は女性の身体のことをなんとなく理解しているつもりでしたが、整理や妊娠のメカニズムにしての知識を深める努力はしていなかったです。
男性も知っておきたい、妊娠出産の基本的なこと
その後、不妊治療の薬を飲み始めてから無事に妊娠がわかりました。
妊娠検査薬を持ってした妻は本当に嬉しそうでした。
ドラマなどで見るワンシーンに私もなんとも言って良いのが分からず「おお~そうなのか~」と微妙なリアクションをしてしまった記憶があります。
それから徐々に大きくなっていく妻のお腹を触ったり、足で蹴った感触など男性にとっては不思議でしかなかったです。
お腹に子どもがいるって一体どんな感じなのだろうと生命の神秘を感じるとともに育休ギリギリまで満員電車で通勤している女性の強さに日々関心していました。
また、女性の生理周期や妊娠に関する知識がほとんどないまま、「子どもがほしい」と軽々しく言っていた自分の無責任さに気づかされたのは、妊娠8ヶ月のある日でした。
私:「ねぇ、“つわり”っていつ来るの?」
妻:「……は?」
空気が一変しました。雷が落ちたような沈黙の中で、妻が絞り出すように言いました。
「もうとっくにつわりなんか終わってるんですけど。何も知らないの!?!?」
怒りと呆れが入り混じった妻の顔は、今でも忘れられません。
男性は女性の身体のことを学ばずに大人になってしまうことが多く、本当に反省すべき点だと痛感しました。
世の男性たちには、「結婚したらゼクシィ、子どもができたらたまごクラブの前に、“女性の身体について学びましょう”」と伝えたいですね。
もちろん、仕事も早く切り上げて家事などの負担がないように日々気遣っていたつもりですが、根本的な妊娠出産女性の身体について学ぶ機会は男性にはないので夫婦になったらしっかり話あっておくのが大切です。
妊娠検査薬を持ってした妻は本当に嬉しそうでした。
ドラマなどで見るワンシーンに私もなんとも言って良いのが分からず「おお~そうなのか~」と微妙なリアクションをしてしまった記憶があります。
それから徐々に大きくなっていく妻のお腹を触ったり、足で蹴った感触など男性にとっては不思議でしかなかったです。
お腹に子どもがいるって一体どんな感じなのだろうと生命の神秘を感じるとともに育休ギリギリまで満員電車で通勤している女性の強さに日々関心していました。
また、女性の生理周期や妊娠に関する知識がほとんどないまま、「子どもがほしい」と軽々しく言っていた自分の無責任さに気づかされたのは、妊娠8ヶ月のある日でした。
私:「ねぇ、“つわり”っていつ来るの?」
妻:「……は?」
空気が一変しました。雷が落ちたような沈黙の中で、妻が絞り出すように言いました。
「もうとっくにつわりなんか終わってるんですけど。何も知らないの!?!?」
怒りと呆れが入り混じった妻の顔は、今でも忘れられません。
男性は女性の身体のことを学ばずに大人になってしまうことが多く、本当に反省すべき点だと痛感しました。
世の男性たちには、「結婚したらゼクシィ、子どもができたらたまごクラブの前に、“女性の身体について学びましょう”」と伝えたいですね。
もちろん、仕事も早く切り上げて家事などの負担がないように日々気遣っていたつもりですが、根本的な妊娠出産女性の身体について学ぶ機会は男性にはないので夫婦になったらしっかり話あっておくのが大切です。
出産後の生活と気づき
長女の出産自体は、以前のブログにも書いたとおり、とてもスムーズで安産でした。けれども、出産後の関わり方や生活に関しては、反省点ばかりです。
妻は実家に里帰りしました。といっても、我が家から自転車で10分ほどの距離。何かあればすぐに駆けつけられる距離でした。」
しかし私は、その“近さ”に甘えてしまっていました。
「義理の両親もいるし、なんとかなるだろう」──そう思い、私は独身時代に戻ったかのようにフルタイムで仕事に没頭し、夜や土日もアポイントや事務処理に追われていました。
もちろん、2日に一度は時間を作って長女の様子を見に行っていました。とはいえ、生まれたばかりの娘に「可愛いでちゅね〜」などと軽くあやす程度で、後はほとんど妻や義母に任せっきり。
一緒に過ごしていれば妻の体調の変化にも気づけたかもしれませんが、実家にいたため、どれほど大変な思いをしていたのか、当時の私は把握できていませんでした。
出産は夕方で、赤ちゃんと一緒に過ごす母子同室の病院だったこともあり、妻は生まれた直後から数時間ごとに起きる赤ちゃんのお世話で眠れない状態が続いていました。昼夜逆転の生活。泣き止まない赤ちゃん。さらには産後のホルモンバランスの乱れ。
そうした積み重ねの中で、出産してから妻は次第に不眠症のような状態になり、精神的にも疲弊していたったとのことです。
心療内科で薬を処方されたことを聞いたときは自分がもっと積極的にサポートできていればと反省しました。
妻は実家に里帰りしました。といっても、我が家から自転車で10分ほどの距離。何かあればすぐに駆けつけられる距離でした。」
しかし私は、その“近さ”に甘えてしまっていました。
「義理の両親もいるし、なんとかなるだろう」──そう思い、私は独身時代に戻ったかのようにフルタイムで仕事に没頭し、夜や土日もアポイントや事務処理に追われていました。
もちろん、2日に一度は時間を作って長女の様子を見に行っていました。とはいえ、生まれたばかりの娘に「可愛いでちゅね〜」などと軽くあやす程度で、後はほとんど妻や義母に任せっきり。
一緒に過ごしていれば妻の体調の変化にも気づけたかもしれませんが、実家にいたため、どれほど大変な思いをしていたのか、当時の私は把握できていませんでした。
出産は夕方で、赤ちゃんと一緒に過ごす母子同室の病院だったこともあり、妻は生まれた直後から数時間ごとに起きる赤ちゃんのお世話で眠れない状態が続いていました。昼夜逆転の生活。泣き止まない赤ちゃん。さらには産後のホルモンバランスの乱れ。
そうした積み重ねの中で、出産してから妻は次第に不眠症のような状態になり、精神的にも疲弊していたったとのことです。
心療内科で薬を処方されたことを聞いたときは自分がもっと積極的にサポートできていればと反省しました。
見えない不安との向き合い
妻が出産したのは総合病院でした。小児科が隣接しており、赤ちゃんに万が一のことがあってもすぐに対応してもらえる環境。選ぶうえで安心材料の一つではありました。
しかし実際には、ハイリスク妊婦の受け入れが多いため、医師や助産師、看護師たちは重症ケースへの対応に追われていて、健康な妊婦へのサポートが後回しになるという現実がありました。
異常のなかった妻は、最低限の説明とケアしか受けられず、初めての出産に戸惑いながらも、自分で調べ、自分で判断しなければならない場面が多かったようです。
体はボロボロ、ホルモンバランスも大きく乱れており、心まで追いつかない。
まさに、嵐の中を一人で歩いているような感覚だったと話してくれました。
実家に戻ってからは、私や家族ができる限りのサポートをしていたつもりです
私も寄り添おうと努め、実家の母も家事を担ってくれ、休める環境を整えたつもりでした。それでも、妻の心は少しずつすり減っていきました。
「なんでこんなに気持ちが沈むんだろう」そう妻が感じていた頃、次第に食事もとれなくなり、未来に希望が見えなくなってしまったのです。
口に食べ物を運ぼうとしても喉で詰まる。食べなければ体がもたないとわかっていても、どうしても食べられない。気力・体力が低下し、気持ちも落ち込んでいったそうです。
出産後の数日間のできごとでしたが、本当に長く辛い期間だったそうです。
しかし実際には、ハイリスク妊婦の受け入れが多いため、医師や助産師、看護師たちは重症ケースへの対応に追われていて、健康な妊婦へのサポートが後回しになるという現実がありました。
異常のなかった妻は、最低限の説明とケアしか受けられず、初めての出産に戸惑いながらも、自分で調べ、自分で判断しなければならない場面が多かったようです。
体はボロボロ、ホルモンバランスも大きく乱れており、心まで追いつかない。
まさに、嵐の中を一人で歩いているような感覚だったと話してくれました。
実家に戻ってからは、私や家族ができる限りのサポートをしていたつもりです
私も寄り添おうと努め、実家の母も家事を担ってくれ、休める環境を整えたつもりでした。それでも、妻の心は少しずつすり減っていきました。
「なんでこんなに気持ちが沈むんだろう」そう妻が感じていた頃、次第に食事もとれなくなり、未来に希望が見えなくなってしまったのです。
口に食べ物を運ぼうとしても喉で詰まる。食べなければ体がもたないとわかっていても、どうしても食べられない。気力・体力が低下し、気持ちも落ち込んでいったそうです。
出産後の数日間のできごとでしたが、本当に長く辛い期間だったそうです。
見えない身体の変化
その頃には、「足のムズムズ症候群(レストレスレッグス症候群)」のような症状にも悩まされていたようです。実際に何か異常があるわけではないのに、足裏がひたすら痒くて、気持ちが悪くて、夜も眠れない。ただでさえ疲れているのに休めない──この症状は本当に辛かったそうです。
赤ちゃんはよく寝てくれる子だったにもかかわらず、妻の心と体は相当疲弊していました。今、妻はこう語ります。「出産してから1年くらいは長女のことを本当に愛せるか自身がなかった、薬を飲まなくなった時の心臓のバクバク感は今も忘れなれない恐怖でしかなかった、この話は、時間が経ってようやく話せるようになった」と。
それほど、あの時期の記憶は心の奥深くに刻まれているのだと思います。出産とは、命を生み出す壮絶な営みです。そしてそれは、出産の瞬間で終わりではなく、その後の回復と育児という長く続く道の始まりでもあります。
どれだけ周囲が支えても、本人の中で起こる心と体の変化は、他人には完全には理解できません。だからこそ、出産を終えた女性に対して「お疲れ様、終わったね」ではなく、「ここからも一緒に歩いていこう」と伝えることが何より大切なのだと、妻の経験を通して私自身も深く学びました。
そして妻はこう言います。「あの産後うつを乗り越えた経験があるからこそ、今まさに苦しんでいる人の気持ちが痛いほどわかる。あのときの自分のように、見えない不安や孤独に包まれている人に、そっと寄り添えるようになった」と話てくれました。
赤ちゃんはよく寝てくれる子だったにもかかわらず、妻の心と体は相当疲弊していました。今、妻はこう語ります。「出産してから1年くらいは長女のことを本当に愛せるか自身がなかった、薬を飲まなくなった時の心臓のバクバク感は今も忘れなれない恐怖でしかなかった、この話は、時間が経ってようやく話せるようになった」と。
それほど、あの時期の記憶は心の奥深くに刻まれているのだと思います。出産とは、命を生み出す壮絶な営みです。そしてそれは、出産の瞬間で終わりではなく、その後の回復と育児という長く続く道の始まりでもあります。
どれだけ周囲が支えても、本人の中で起こる心と体の変化は、他人には完全には理解できません。だからこそ、出産を終えた女性に対して「お疲れ様、終わったね」ではなく、「ここからも一緒に歩いていこう」と伝えることが何より大切なのだと、妻の経験を通して私自身も深く学びました。
そして妻はこう言います。「あの産後うつを乗り越えた経験があるからこそ、今まさに苦しんでいる人の気持ちが痛いほどわかる。あのときの自分のように、見えない不安や孤独に包まれている人に、そっと寄り添えるようになった」と話てくれました。
これから妊娠・出産を迎えるご夫婦へ
あの苦しかった日々も、無駄ではなかった。そう思えるようになったことが、今の妻にとって何よりの救いなのかもしれません。今、つらい気持ちを抱えている方に、少しでも「一人じゃない」と感じていただけたら嬉しいです。そして、周囲の方々にとっても、大切な人をどう支えるかを考えるきっかけになればと願っています。
知っておきたい出産・不妊治療と医療保険のこと
加入中の医療保険の給付
私たち夫婦は、長女の出産時に自然分娩で特に問題もなく出産をおえましたので、加入していた医療保険からの給付はありませんでした。
一般的に、自然分娩は「正常分娩」として保険給付の対象外となるケースが多いです。しかし、切迫早産や帝王切開、吸引分娩など、医師の処置が必要なケースでは給付金の対象になる可能性があります。
出産は予測が難しいため、事前に保険の内容を確認し、必要に応じて保障内容を見直すことが重要です。
一般的に、自然分娩は「正常分娩」として保険給付の対象外となるケースが多いです。しかし、切迫早産や帝王切開、吸引分娩など、医師の処置が必要なケースでは給付金の対象になる可能性があります。
出産は予測が難しいため、事前に保険の内容を確認し、必要に応じて保障内容を見直すことが重要です。
不妊治療と保険適用の拡大
2022年4月から、不妊治療が公的医療保険の対象となり、体外受精や顕微授精などの生殖補助医療も保険診療として受けられるようになりました。
これにより、治療費の自己負担は大幅に軽減され、高額療養費制度の適用も可能となっています。ただし、年齢や治療回数に制限があるため、詳細は医療機関や自治体、保険会社への確認が必要です。
例えば、40歳未満の女性は保険適用で最大6回、40歳以上43歳未満では最大3回までの胚移植が可能とされています。
これにより、治療費の自己負担は大幅に軽減され、高額療養費制度の適用も可能となっています。ただし、年齢や治療回数に制限があるため、詳細は医療機関や自治体、保険会社への確認が必要です。
例えば、40歳未満の女性は保険適用で最大6回、40歳以上43歳未満では最大3回までの胚移植が可能とされています。
先進医療と保険の関係
不妊治療で使われる先進医療(タイムラプス撮像法、SEET法など)は全額自己負担ですが、一部の保険会社では先進医療特約の給付対象となる場合もあります。
適用条件は各社で異なるため、事前に保険会社に確認することが重要です。
また、東京都では、保険診療と併せて実施した先進医療に対して、費用の一部を助成する制度もあります。妊娠中に切迫早産のリスクがあることを医師から指摘され、入院が必要となこともあります。出産に備えて保険を見直すことで、予期せぬ事態にも安心して対応できる体制を整えることが可能です。
適用条件は各社で異なるため、事前に保険会社に確認することが重要です。
また、東京都では、保険診療と併せて実施した先進医療に対して、費用の一部を助成する制度もあります。妊娠中に切迫早産のリスクがあることを医師から指摘され、入院が必要となこともあります。出産に備えて保険を見直すことで、予期せぬ事態にも安心して対応できる体制を整えることが可能です。
メッセージ
妊娠や出産、不妊治療は、多くの夫婦にとって大きなライフイベントです。
これらの出来事は、誰にでも起こり得るものであり、特別なことではありません。
そのため、事前に医療保険の内容を確認し、必要に応じて見直すことで、安心してライフイベントを迎えることができます。
また、不妊治療に関しては、保険適用の拡大により、経済的な負担が軽減されるようになりました。
しかし、治療内容や回数に制限があるため、医療機関や保険会社と相談しながら、最適な選択をすることが重要です。
人生の大切な節目に備えて、医療保険の見直しや情報収集を行い、安心して未来を迎えましょう。
これらの出来事は、誰にでも起こり得るものであり、特別なことではありません。
そのため、事前に医療保険の内容を確認し、必要に応じて見直すことで、安心してライフイベントを迎えることができます。
また、不妊治療に関しては、保険適用の拡大により、経済的な負担が軽減されるようになりました。
しかし、治療内容や回数に制限があるため、医療機関や保険会社と相談しながら、最適な選択をすることが重要です。
人生の大切な節目に備えて、医療保険の見直しや情報収集を行い、安心して未来を迎えましょう。